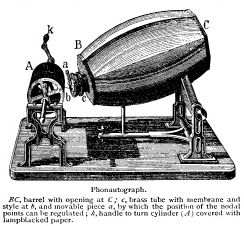1.音楽の入手経路の変化-オンライン上の音楽たち
20世紀末から21世紀初頭にかけて音楽文化は様々な点で変化した。すでに90年代半ばまでに、記録メディアとしてのCD規格はファミリー・メンバーを増やし、そこに記録される音楽はPC上で扱われることでデジタル情報として操作されるものとなっていた。音楽が記録されるメディアと音楽との物理的な結びつきは脆弱化し、音楽をデジタル情報として扱うことで、音響生産・流通・消費テクノロジーは一般大衆化していた。消費者が、自分の好きなように(デジタル情報としての)音楽を扱える状況は整っていたわけだ。さらに(日本では)90年代後半にインターネット・インフラが整い、P2P技術やデジタル・コンテンツ利用技術が開発されることで、音響生産・流通・消費テクノロジーの一般大衆化の傾向には拍車がかけられたと言えよう。
「音楽のネットワーク化」とは何だろう?それは、「音楽のデジタル化」によってすでに90年代半ばまでに可能となっていた、音響生産・流通・消費テクノロジーの一般大衆化の傾向に、1)更に何か新しい性質を付加したのか、それとも 2)その傾向を更に「激化」させたに過ぎないのか、あるいは 3)「その傾向を激化させること」こそが「ネットワーク化」の本質だったのか、どれなのかは即断できない。これは「インターネット・テクノロジー」の文化的位置づけにまつわる大きな問題だし、何よりもまだ、判断するには時期尚早の問題だろう。とにかく、インターネットのインフラ環境が整備されることで、音楽を入手するコストは安価になり、音楽を入手する経路や音楽が流通する経路はそれまでとは比べ物にならないくらい多様化したことは確かだろう。
以下ではとりあえず、店頭でCDを買うことこそが普通の音楽入手方法だった10代を過ごした私が、1990年代末以降の音楽文化の変化の中で目に付いたものを列挙しておくに留めておきたい。
以下の参考文献
ナップスターについては、シリコンバレーの狂騒に包まれていたナップスター社の設立から終焉に至る活動を、メン2003が存分に伝えてくれている。また、1990年代以降の日本の音楽を取り巻く状況については烏賀陽2005a;烏賀陽2005bが参考になる。しかし、それ以降の、パッケージ・メディアに依存しない音楽のあり方について考えるためには、津田2004と津田のブログ
音楽配信メモが最重要となる。音楽配信の日本における売上実績の数値については、本文中にもある通り、
社団法人日本レコード協会のウェブサイトを参照した。また、iPodに関する言及はレヴィ2007を参照した。
1.CD-R
PCでCD-Rを作成できるようになったこと、(パッケージは複製できないけれども)同じ音質のCD(CD-R)を複製・作成できるようになったこと。これは衝撃的な経験だった。車で聴くために、ビーチ・ボーイズやT.Rexなどその頃の私が好きだった洋楽と、友達のバンドの音源を一緒にしたマイ・ベストを作成したのが最初だったと思う。(著作権法上「私的複製」することは認められているので、CD-RやMP3を用いた音楽CDのコピーの全てが「違法」ではない。)CD-Rは、間違いなく、消費者が好きなように音楽を扱えるようになったテクノロジーだ。CDジャケットやCDレーベルは無理だが、元のCDと全く同じデジタル情報が記録されたCD-Rを消費者個人が作れるようになったのだから。
とはいえ勿論、CD-Rはあらゆる方面から歓迎されたわけではない。CD-Rを用いた「違法」コピー(とファイル交換ソフト)は、Jポップバブルの崩壊(2000年代初頭)の主な原因とされた。日本のJポップバブルが頂点に達した1998年に、オーディオ・ディスク生産額はピークを迎え約6075億円に達した。それ以後、音楽CDの売り上げは毎年下がり続けており、2007年のオーディオ・ディスク生産額は約3333億円である。また、私は、先日、
オリコンシングルチャートで20位が3000枚未満、という衝撃的なニュースを知った。Jポップバブルは崩壊し、CDの売り上げは減少の一途を辿っているのだ。その原因が何かは一概には言えまい。そもそも90年代のJポップバブルが「バブル」でしかなかったのかもしれないし、音楽産業や日本の文化構造の質的な変化が原因かもしれないし、やはりCD-Rによる「違法」コピーが原因だったのかもしれない。
さしあたり今は次のように考えておきたい。CD-Rが音楽に与えた影響(音楽産業に与えた悪影響)をどのように判断すべきかは、判断する人間の倫理観というよりも、音楽産業(狭くはCD小売業)に対して持つ利害関係によって異なるだろう。CD-RはCD売り上げ減少の一因ではあろうが、だからといって今更CDを絶滅させることは不可能だろうし、コピーー不可能な(はずの)CCCDの導入は失敗だった。CD規格として認められず、しばしば通常のCDプレイヤーで再生できなかったCCCDは、CDをリリースするミュージシャンや消費者から嫌われ、消費者が(少なくとも私が)CDから遠ざかる一因となった。CD-Rが音楽に与えた変化はまだ沈静化したわけではないので即断は避けるが、自分の10代にとって重要な意味を持つCD小売業の将来は、ある種のノスタルジックな気分も込めつつ、注目していきたい。
2.ファイル交換、P2Pソフト
1999年初頭に公開されてすぐに爆発的に流行した、ファイル交換ソフト「ナップスター」は、音楽流通経路にある種の革命を引き起こすきっかけになった。ナップスターを使うと、登録ユーザーのPCにあるMP3ファイルがデータベース化され、ユーザーはそれを検索して自分が聴きたい曲をダウンロード(他の登録ユーザーと「共有」して「コピー」)できた。ナップスターは爆発的に流行し、最盛期にはアメリカの大学生のうち73%が利用したという調査結果(2000年5月)すらある。ナップスターを、廃盤になって入手できない過去の音楽を入手するために積極的に用いた音楽マニアもいたし、ナップスターの理念(自由で無料の音楽、プロモーションとしての音楽交換等々)を支持したミュージシャン(オフスプリングやパブリック・エナミーのチャック・Dなど)もいた。しかし音楽業界や何人かのミュージシャン(メタリカなど)はナップスターを厳しく批判し、法的にもナップスターは否定された。というのも、ナップスターは、著作権を無視した違法なファイル交換が日常的に行われる場所でもあったからだ。一説には流通量の約90%が違法だった。ナップスターは1999年12月に全米レコード工業会(RIAA)に提訴され、その裁判闘争の間に徐々に影響力を失い、2001年7月にはサービスを停止した。
ナップスターは、良くも悪くも、その後登場した、サーバーを用いない新しいタイプのP2Pソフトウェア(GnutellaやKaZaaなど)の先駆的存在だ。ナップスターがなくなっても違法ファイル交換が根絶されたわけではない。また違法行為を可能とするツールである以上、無条件にP2P技術を肯定できるわけでもない。しかし少なくとも、ナップスターは、インターネットを通じてコンピュータを接続してファイルを共有することで、レコード会社を経由せずに、音楽マニアたちが独自の音楽流通ネットワークを作り出すことを可能にした技術でもある。P2P技術は人々が独自の(音楽流通)ネットワークを作り出せるツールでもあった。「テクノロジーは音楽を大衆化して個人化した」という物語が安易なことは自覚している。しかし私は、レコード会社を経由せずに作られる音楽流通ネットワークが今後どのように展開していくのか(そもそもそのようなネットワークは成立するのかどうか)、楽しみにしている。
3.You Tubeなどの動画共有サイト
YouTubeは2005年2月15日に設立されたサービスだ。今の私たちの生活への浸透具合を考えれば、驚くほど最近の設立だろう。YouTube以降、私は、新しいCDや音楽を聴いてみたい時には、レコード屋での試聴やラジオやテレビでのプロモーションを待つのではなく、まず、You Tubeで検索してみるようになった。音質は悪くとも、自分の家で好きな時に何度でも、どの店にあるよりもたくさんの種類の音楽と曲を、無料で試聴できるからである。
YouTubeで試聴して気にいったものはCDもしくは高音質のデジタルデータを購入する。しかし気に入らなかったものは購入しない。当たり前のことだが、このおかげで「買って初めて聴いて、がっかりする」ということがなくなった。
またYouTubeのおかげで、私は、あまり「音だけから音楽を知る」という経験をしなくなった。つまりある音楽を知り始める入り口が、「音だけ」よりも「音+映像」からの場合が多くなった。もちろんこうした経験は初めてではなく、MTVやテレビでのプロモーションからある曲を知る場合もそうだった。しかしYouTubeから音楽を知る機会が増えるにつれ、音楽経験における視覚経験の重要性が飛躍的に高まった。私が新しい音楽を知るきっかけが変質したのだ。
4.ネットラジオ
また、私が最近も個人的に気に入っているサービスに「ネットラジオ」というものがある。この種のサービスでは、たいてい、自分専用のラジオ局を作ることができる。例えば自分の好きなミュージシャンを一人指定すると、自分専用のネットラジオ局ができて、自分が選んだミュージシャンの音楽と似た傾向の音楽を勝手に選んで再生してくれる。そこでは、気に入った音楽の情報を教えてくれるページや、その音楽をオンラインで購入できるページへのリンクが用意されている。海外では
Pandora,
Jango,
AccuRadioなどのサービスが有名だが、日本では著作権の問題がありほとんど普及していない。(唯一知っている似たようなサービスに、
Yahoo!ミュージック - サウンドステーションがあるが、あまり融通が利かず使いづらい印象がある。また、日本版の
Last.fmもあるが…。)
この先どうなるかはよく分からないし、そもそも日本で可能なサービスなのかどうかも分からないが、私個人は今後も楽しんで使っていきたいと思っているサービスである。
5.音楽配信
PCやインターネットというテクノロジーは、違法コピーやファイル交換ソフトという問題をもたらしただけではなく、「音楽配信」という新しい音楽産業ももたらした。音楽配信とはインターネットを通じて(無料の場合もあるが多くの場合は有料で)楽曲を配信するサービスである。サービスそのものの歴史は意外と古く90年代後半から模索されていたが、インターネット上で音楽をコンテンツとして販売する可能性が意識され始めたのは、1998年頃からMP3が普及したことがきっかけだろう。1999年のナップスター騒動の影響もあり、米国で著作権管理の問題をクリアした音楽配信サービスが始まるまで少し時間がかかったが、2001年12月には、Rhapsodyなど幾つかの合法な会員制音楽配信サービスがスタートした。
とはいえ、音楽配信サービスが一般メディアでも話題になるようになったのは、2003年4月にアップル社のiTune Music Store(現iTune Store)がサービスを開始してからだ。1曲99セントでダウンロード販売を行ったiTMSは、サービス開始後一週間で100万曲、16日間で200万曲、年末までに2500万曲をダウンロード販売した。カタログ数が豊富で手頃な価格(日本では1曲150-200円)で、ユーザーが使いやすいデジタル著作権保護機能を提供した米国では、最もメジャーな音楽配信サービスとなった。
その後、Amazon.comやiTunes PlusからDRM-Freeの音楽ファイルが販売されるようになった。デジタル著作権保護機能を持たないデジタル・ファイルが消費者に対して販売されるようになったのだ。安価で使い勝手が良いならば合法なデジタル音楽ファイルを購入しようとする消費者は多いだろう。DRM処理されていないファイルなので、消費者がファイル交換ソフトを通じて無数の人間に配布することは可能だが、そうして無数の人間にコピーされたファイルには電子透かしが組み込まれており、元々のデジタル・ファイルを流出させた人間が誰かは分かるようになっており、著作権侵害という違法行為に対する対策は取られている。とはいえ、自分自身のPC同士の間なら何度でもコピーできるなど、DRM-Freeの音楽ファイルの利点は計り知れないというべきだろう。
また、「サブスクリプション・サービス」と呼ばれるサービスがある。これはオンライン上の音楽をストリーミングでダウンロードして聴き放題というタイプの音楽配信サービスで、米国では既に2001年にRhapsodyが登場している。日本でも、2006年4月から、合法化されてブランド名だけが残ったナップスター社と、本社が潰れる前に独立した日本のタワーレコード社が合同で提供している。毎月の会費を払い続けている間は、事業者が用意した楽曲を全て自由に聴いて自由に自分のパソコンにダウンロードできるサービスが、今後どのように成長していくのかは分からないが、インターネット環境の中で維持される音楽産業の一形態として重要である。
これらの音楽配信事業がどの程度の速度で音楽産業界を支配していくのかは分からないが、インターネット環境さえ整備されていれば音楽を入手できるのだから、今後、商品としての音楽が流通するメインの経路となるのではないだろうか。
6.ミュージシャンのレーベル離れ
こうした傾向から、私は、音楽産業としてのレコード産業は消滅するかもしれないが、音楽産業と、そして何よりも「音楽」そのものはなくならないだろう、と考えるようになった。レコード会社はなくなっても音楽家は活動し続けてくれることを示す事例だからだ。
私が考えているのは、有名なミュージシャンが、自分の新作を無料で提供したりウェブサイトから直接販売するようなケースだ。例えば
プリンスは、2007年7月15日にイギリスの「Daily Mail」紙という新聞の日曜版付録として、無料で、自分の新作アルバム『Planet Earth』を配布した。プリンスはこのアルバム配布を「マーケティング」の一環として位置づけている。またナインインチネイルズは
自分のウェブサイトから自分の作品を直接ダウンロード販売している。あるいは少し違う事例だが、
マドンナは2007年7月に、所属レーベルのワーナー・ミュージックを離れ、レコード会社ではなく、イベント/ライブ運営を手掛ける「ライブ・ネーション」という企業に移籍した。こうしたやり方で彼ら/彼女らは、ライブなどCD売り上げ以外の部分で利益を上げようとしたり、レコード会社を通さずに直接消費者に音源を売ることで利益を上げようとしているのかもしれない。
CDはすでにプロモーションの道具でしかないのかもしれない。こうしたやり方で利益を出せるのは、すでにある程度有名になったミュージシャンだけではないかとも思うし、こうしたやり方で新たに有名なミュージシャンが作られるプロセスが私には想像できない。とはいえ、新しい音楽を聴くためにはレコード会社から販売されるレコードやCDを購入する以外には方法がないのが当然だった人間にとっては、こうした傾向は、この後の展開を楽しみにさせてくれるもので、大いに色々なミュージシャンに試みて欲しいものの一つである。。
7.DAP (Digital Audio Player)
音楽配信サービス成立の(そしてMP3普及の)背景の一つは、DAPが普及したことだ。現在のDAPの嚆矢となったのは1998年に市販されたMPMAN(仕様は内蔵32MB; 64MB)だが、DAPが一般に認知されたのは、アップル社のiPodがきっかけだ。2001年11月に販売されたiPodは、当時ではすば抜けて大容量だった(5-20GB)し業界最低ラインの容量単価の商品だった。そのiPodは、発売後2ヶ月で12万5千台以上を販売した大ヒット作となった。iPod、それに先立って2001年1月に公開された音楽管理ソフトiTunes、そして2003年にサービスを開始したiTune Music Store(日本では2005年8月にサービスが開始された)、アップル社の音楽関連事業は、商業的に大成功した、音楽を入手する新しいやり方だ。音楽関連のマーケットにおける「アップル」という商標使用の問題、
SonyのWalkmanとの競争など、個人的に関心のある話題も多いが、その最大の文化的意義はなんだろうか?まだ明確には言明できまいが、例えばレヴィ2007のように、(文字通り自分音楽ライブラリー全ての曲を、あるいは、文化的構造を「シャッフル」すること、と考えても構わないかもしれない。
2.音楽配信:日本の場合
日本では「音楽配信」は、米国とはかなり違う展開を見せている。日本でiTMSがサービスを開始したのは2005年8月で、その他の国産音楽配信サービスも含めて、有料音楽配信売り上げが増えてきたのは2005年以降のようだ。
社団法人日本レコード協会が公開している
「有料音楽配信売上実績」の統計は2005年以降のものだが、それによると、日本の有料音楽配信は、2005年から2007年にかけて、343億円→535億円→755億円と急激に成長している。同時期のオーディオ・レコードの売り上げ額は3672億円→3516億円→3333億円と継続的な微減状態だ。2006年の有料音楽配信の売上げ額(535億円)は、初めてCDシングルの売り上げ額(508億円)を上回った。
しかし日本の音楽配信では、インターネットを通じてPCにダウンロードする音楽配信より、「着メロ」や「着うた」など携帯電話向けの市場の方が圧倒的に大きい。ケータイ系とパソコン系の市場規模は、2004年は約20倍、2005年以降も約10倍近い開きがある。
これは何を意味するのだろう?詳しく分析できているわけではないが、これもまた音楽入手経路が多様化した帰結の一つなのだろう。個人的には音質は悪いし料金も高いケータイ系の音楽配信には興味はないが、ケータイ系の音楽配信は、独自の進化を遂げた日本のケータイ文化における優れたサービスだ。おそらくそもそも目的が違うケータイ系とパソコン系の音楽配信サービスの優劣を比べることにはあまり意味がないのかもしれない。ケータイ系の音楽配信が持つ、パソコン系の音楽配信とは違う存在意義については、ケータイ系の音楽配信に詳しい誰かの考察を待つことにしたい。